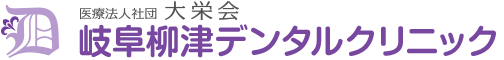嚥下機能が低下する原因と予防ケア

こんにちは。
岐阜柳津デンタルクリニック、歯科衛生士の飯田です。
皆さまは「嚥下(えんげ)」という言葉を知っていますか?
食べ物や飲み物を飲み込む動作のことで、この機能は年齢に関係なく低下することがあります。
今回は、年代ごとに異なる嚥下機能低下の原因と、毎日の生活でできるケアについてお話しします。
嚥下障害とは?
嚥下障害とは、お口の中の食べ物や飲み物をうまく飲み込めない状態をいいます。
嚥下障害の症状は、食べ物が喉に引っかかる感覚や痛み、体重の減少、食事のときのむせがあります。
本来、飲食物は咽頭と食道を通って胃に送られますが、嚥下障害により誤って飲食物が気管に入る「誤嚥」が生じることがあります。
誤嚥した飲食物や唾液に含まれた細菌が気管を通って肺に入ると、「誤嚥性肺炎」を引き起こす原因となるため注意が必要です。
年代別の嚥下機能低下
20〜30代
スマホやパソコンの長時間使用により前かがみの姿勢になりやすく、首のカーブがまっすぐになる「ストレートネック」になりがちです。
その姿勢が原因で、嚥下に必要な筋肉の動きが制限され、飲み込みにくくなることがあります。
また、むし歯や歯周病があるとお口の中に細菌が増え、細菌を含んだ唾液などが誤って気管に入ると、「誤嚥性肺炎」となる恐れがあります。
40〜50代
年齢とともに筋力が低下し、唾液の分泌量も減少していきます。
また、飲み込む反射が鈍くなるため、気付かないうちに誤嚥を起こしてしまうことも。
これによりお口が乾燥しやすくなり、食べ物をスムーズに飲み込めなくなります。
60代以上
高齢になると、むし歯や歯周病によって歯を失いやすくなり、噛む力や舌の動き、味覚や唾液分泌量などが総合的に低下します。
その結果、食べ物をうまく食道に送れず、食べ物や唾液が喉に残ることが増えてしまいます。これが誤嚥のリスクを高める原因となります。
年齢別ケアのポイント
嚥下機能の低下は、日頃のケアで予防できます。
20〜30代
食べるときは背筋を伸ばし、よく噛んで食べましょう。
また、食後は必ず歯みがきを行い、お口の中を清潔に保つことが大切です。
40代以上
舌や唇、喉の筋肉を鍛える「お口の体操」がおすすめです。
また、定期的に当クリニックで検診を受けることで、ささいな変化にも早期に気付くことができます。
毎日の習慣で飲み込む力を守ろう
嚥下力を守るためには早い段階から対策することが大切です。
姿勢を整えたり、正しく歯みがきをしたり、お口の筋肉を意識して動かしたりすることで、いつまでもしっかり食べられるお口を保つことができます。
当クリニックでは、嚥下に関するご相談も受け付けています。気になる症状があれば、ご相談ください。